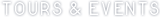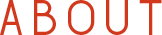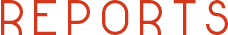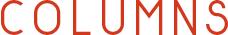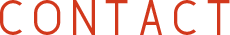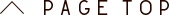梵寿綱のユートピア☆ケンチク vol.2
日時:2018年2月12日(月)9:30~14:00
見学場所:《ルボワ平喜》、《ヴェッセル・きらめく器》、《ラポルタ和泉》、《マインド和亜》、《ドラード和世陀》
参加者:13名
スペシャルゲスト:梵寿綱(建築家)
ナビゲーター:和田菜穂子
*****
梵寿綱さんの手がけた“仕事”を巡るツアーでした。私にとっては、昨年の3/12に開催されました「梵寿綱と巡る『生命の讃歌』トークツアー」がインターンとなって初めて参加したツアーでした。なので、梵さんの建築には思い入れがあります。
まずは池袋駅から徒歩5分くらいの場所に《ルボワ平喜》(1979)、《ヴェッセル・きらめく器》(1990)があります。ここでは和田先生から梵さんについての基本的な情報のレクチャーがありました。参加者の皆さんにはクイズを出して一緒に考えました。梵さんの建築はよくガウディと比較されることが多いのですが、ガウディは自分の作りたいものを腕の立つ職人に指示して作っていきます。それに対して、梵さんの場合は複数人のアーティストに全て任せて、アーティスト同士の相互的な協調の結果としての建築を作り出そうとしているのです。さながらジャズのセッションのような建築です。
池袋から代田橋へ移動し、《ラポルタ和泉》(1990)と《マインド和亜》(1992)へ向かいます。《マインド和亜》ではオーナーの石井さんに特別に案内していただき、共有部だけでなく屋上から住戸、地階まで様々なところを見学させていただきました。石井さんも施工会社で働いていたのですが、鉄とコンクリートだけの建築は冷たく人が暮らすには適していないのではないかという問題意識を梵さんと共有していたそうです。この建築には通常の3倍は人の手がかけられているから、その分あたたかい建築になっているのです。また、無駄な装飾に見えるものたちもアーティスト同士で共有されたテーマに沿って心地よい統一感を持った空間が作り出され、素材の選択など人々が心地よく暮らすための建築となっているのだと感じました。
最後に《ドラード和世陀》(1983)に移動し、1階のアンティーク時計店で梵さんのレクチャーを聴きました。先日84歳になられた梵さんですがまだまだ元気です。建築を作るにあたって、与えられた敷地や条件でそこに建てる意味とは何か?ということを考えていらっしゃいます。一年前にお話しした時のことを思い出し、私も建築に関わっていく身として、社会での意味を問いながら活動を続ける梵さんの姿勢を見習いたいなと改めて感じました。
レポート:中村 竜太(学生インターン)
早稲田大学 創造理工学部 建築学科3年