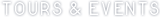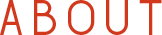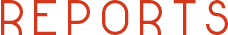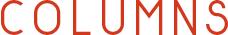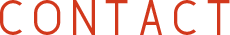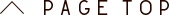レクチャー付ツアー「中銀カプセルと茶室空間」vol.6 & 7
【vol.6】 2017年7月1日(土) 9:30~12:30 参加者:5名
【vol.7】 2017年7月1日(日)13:30~16:30 参加者:5名
見学場所:《ニュー新橋ビル》、《静岡新聞・静岡放送東京支社》、《中銀カプセルタワー》
ナビゲーター:和田菜穂子
今回のレポートは、vol.6に随行した学生インターンの中村竜太くんによる初めてのレポートです。
*****
和田菜穂子先生がナビゲートする「中銀カプセルと茶室空間」ツアーはこれまで何度か開催されていますが、私はアシスタントスタッフとして初めて参加しました。メタボリズム運動の中心人物として活躍した黒川紀章の《中銀カプセルタワー》をメインに、松田平田設計の《ニュー新橋ビル》、丹下健三の《静岡放送・静岡新聞 東京支社》を巡りました。
まずは待ち合わせ場所の新橋駅SL広場に隣接する《ニュー新橋ビル》。終戦直後この敷地には露店が所狭しに建つ街並みだったそうです。その路地空間の雰囲気が建築内部で展開しています。テナント部とオフィス部が分けられたファサードや階段周りのタイルのデザインなど、場所によって変化が付いていることを解説によって気づかされました。
次に訪れたのは《静岡放送・静岡新聞 東京支社》です。こちらは丹下健三が設計したメタボリズム建築です。コアとなる円柱とそれに付随するユニットによって増殖可能な建築というコンセプトです。同じく丹下が設計した《山梨文化会館》では増殖後の姿を見ることができます。
いよいよ《中銀カプセルタワー》を見学。外観からでも非常に老朽化した姿、幾つかのユニットには手が加えられている姿が見受けられます。《静岡放送・静岡新聞 東京支社》と同様に、中央コアにユニットがまとわり付く形で、室内で見たビデオによるとそれぞれのユニットは25年ごとに新しいものに交換され、ビル全体として200年は使えるように設計されているそうです。ユニット内部は茶室ほどのサイズ感で、和田先生の解説によればこれは設計者黒川が少年期に茶室で生活したことが影響しているという見解でした。
さて《中銀カプセルタワー》の保存については様々な意見があり、ツアー参加者同士でもディスカッションをおこないました。カプセルの分譲制によって引きおこる各オーナーと管理組合との折衝などを聞き、「建築の保存」は建物そのものの問題というよりは、システムの問題であるように思いました。「建て替えか保存か」の決定がなされないまま、崩壊などの事故がおこる前に、複雑な事情を解決できるような仕組の構築が必要であるように感じました。そして、こうした課題を解きほぐしていくのは、私たち次の世代が担っていかなくてはならない問題だと実感しました。
レポート:中村 竜太
早稲田大学 創造理工学部 建築学科 3年