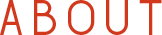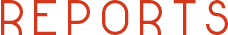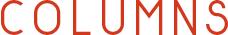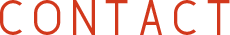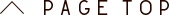原宿駅のコラムをウェブメディア「旅色プラス」に寄稿しました。大正時代に完成した《JR原宿駅舎》、それに昭和戦後の《コーポ・オリンピア》、2003年竣工の《ディオール表参道》の見どころを解説しています。
ここでは、もう1件、近くに建つ《オークラビルディング》(渋谷区神宮前1-22-3)をご紹介しましょう。設計者は鈴木エドワード。1980〜90年代を駆け抜けたその業績を惜しみ、「東京建築アクセスポイント」では、2019年秋の他界後にナビゲーター・磯達雄のもと「鈴木エドワードの『アナーキテクチャー』をめぐる」ツアーを開催しています(ツアーレポートはこちら)。
1981年にオークラビルディングは完成しました。1947年に生まれ、1977年から鈴木エドワード建築設計事務所を主宰する、彼の初期作品にあたります。全体が正方形のグリッドを積み上げた形をしています。窓もそれに合わせています。設計者がハーバード大学大学院や、丹下健三都市建築設計事務所(1975〜76)で学んだ、端正なモダニズムを具現化しているかのようです。
と思いきや、下部ではグリッドがかき取られています。グリッドの空隙で何が起こっているか。打ち放しコンクリートが渦を巻いて螺旋階段となり、その中心にはステンレスの柱がニュッと現れて、コンクリートの荒い断面がさらけ出されています。
理論や機能・構造といった建築を組み立てる骨格の確かさが、綺麗な外見にまで現れる。いわば「美男は性格もいい」とでも言うかのような、人間観・建築観の単調さ。いや、つまらないだけだったら良いのですが、その抑圧性を、嘲笑っているかのようです。正義づら、普通づらしているけれど、もっともっと社会にはさまざまな人間がいてもいいし、いるものではないかと、建築におけるモダニズムの指導的立場に矢を放っています。
鈴木エドワードの作品が一世を風靡したのには、訳があリました。このように彼の作品は、ポストモダニズムの思想の表現でもあったのです。日本のポストモダニズムにはいくつかの傾向がありますが、その一つである「表皮性」の代表選手と言えるでしょう。その後、彼は《渋谷警察署宇田川交番》(1985)や《ジュールA》(1990)などで、その手法が達成できる領域を拡大させていきます。
「表皮性」こそが、哲学者のミシェル・フーコーが「生-権力」として言うような後期資本主義の綺麗な抑圧から人間を自由にするのだ。そんなことが大真面目に信じられていた時代があったのです。
そうした背景の中で、高松伸や北川原温が輝き、伊東豊雄や隈研吾のその後の展開が始まり、槇文彦が現在につながる地位を確立しました。今は見捨てられているような年代、建築家や建築にこそ、大きな流れをつかむヒントがあるのではないかと、私はいつも街を歩きながら思います。それはまだ建築史の教科書になってはいませんが、今の建築や建築家の言葉だけに触れていても理解できないものです。
そして、鈴木エドワードは他のすべての建築家と同様に誠実です。コンセプトだけでさらっと終わっていないのです。
オークラビルディングに近づくと、もう一つの仕掛けが見えてきます。それは「狂ったセパ穴」。「セパ穴」とは、型枠を固定するためのセパレーターに取り付けられたPコン(プラスチックコーン)跡の通称。打ち放しコンクリート仕上げの場合、その穴にモルタルが詰められて、小さな窪みとして表面に現れます。
このビルが完成した1981年の頃、安藤忠雄は、セパ穴も端正に配置した打ち放しコンクリートの作風がファッショナブルと認識されることで、住宅作家からアパレルブランドのビルへと活動の領域を広げていましたが、鈴木エドワードはそれも手仕事で批評。オークラビルディングのセパ穴は一見、規則的なようで、かなり変な位置にあります。特に裏面にまわると、正方形の中にセパ穴が2つあったり、5つ、7つだったりと、相田武文の《サイコロの主題による家》(1973)を連想させるほど。面白い丁寧な力技です。
本稿で「表皮性」という用語を用いているのは、それが相田武文や竹山実のような「表層性」とは異なるからです。「表皮性」は素材感を伴います。例示した高松伸から槇文彦まで、皆がそう。それも教えてくれる鈴木エドワードに賛辞を送りましょう。なんてクレイジーなんだ!